
日本古来からの宗教観としての「神道」と、大和政権以降、政権の正当性を確保しつつ政治的な統治手段として用いられた「神道」とを切り離すのが、「神道」問題に関する現在の一般的な認識である。しかし著者は前者の「神道」=日本固有の文化という主張を、「超歴史的・非歴史的な思考方法」「自国中心主義」「懇意的な歴史解釈」と切って捨てる。
批判の始まりは神道の起源に関する考察である。著者が採るのはオスロ大学のマーク・テーワンの説である。「神道」(ジンドウ)はもともと中国で用いられていた仏教語であるが、そのまま古代日本に輸入された後、14世紀になって「シントウ」に転換した、といいうのがその説の中核である。
多分、後者の神道という言葉の起源に関する歴史的事実は、テーワンの説と大きくは異ならないだろう。問題は、著者がこれをもって、神道全体の起源としていることである。著者によれば、日本固有の文化としての神道は幻想であり、レトリックであり、自国中心主義のドグマに他ならない。そして著者が具体的に批判するのが、柳田国男であり、梅原猛である。
だが、その批判は正直言って説得力に欠く。日本人の底流に流れる心性を否定するのなら、なにより日本人の心についての考察が必要だが、その批判はほぼ形式論理に終始し決して内面に達することがない。日本人の心に内面を深く考察することなしに、そして民俗学や哲学の方法論なくして、どうして柳田や梅原の日本人論を批判できるだろうか。
僕は統治手段としての「神道」に対する著者の厳しい批判はもっともだと思うし、現在の靖国神社のあり方にも批判的な立場をとる。だが、この著者が日本古来の心のあり方を「神道」の名の下に遺棄しようとすることは、彼が批判してやまない権威としての「神道」と通底する独善的なドグマ主義的思考の産物だと思う。
ただ、この本が神道と仏教の宗教史としてはよく整理されていることは事実である。逆に通史としてのあり方に徹していたなら、より異議ある本になったのに残念である。


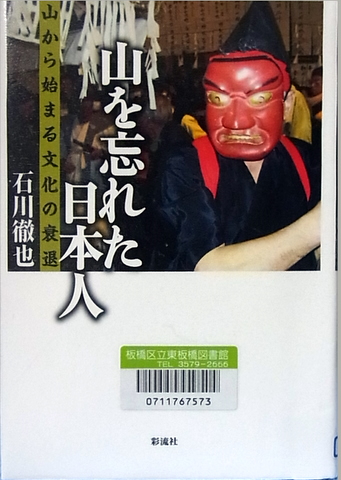
コメント