鶴見俊輔の「限界芸術論」 ちくま文庫
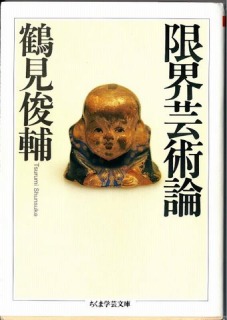
最近アートの展示会から遠ざかっているのは、山登りが忙しいこともあるが、いわゆる純粋芸術に飽きてきたことが大きい。雑誌も芸術新潮は飛ばし読みだが、illustrator誌は毎月号じっくり読んでる。いわゆる括弧付きの「芸術」より、社会で消費される対象としてのデザインの方が、今の僕にはずっと魅力的なのだ。
そのような芸術と非芸術の境界的な作品の志向を意識していた時に恵比寿のアート系書店で見つけたのが、鶴見俊輔の「限界芸術論」だった。題名に感じるものがあったのだが、内容も果たして期待を裏切らなかった。量的にも読み応えのある本だったが、最初から最後まで、とても刺激的な内容だった。
純粋芸術に対する境界的(この本では限界的)な芸術論といえば、赤瀬川原平、横尾忠則、森村泰昌などをすぐに思い浮かべてしまうが、この本を読めばその前に鶴見俊輔という哲学者がしっかりと境界線を引いていたのが分かる。いわゆる純粋芸術の領域はおそらく定義上極めて狭いのだろうが、芸術とそうみなされないモノの間に横たわる限界的な芸術の範囲は広大で常に変化している。
鶴見俊輔はその限界芸術を記述するのに体系的な手法を取らなかった。らくがき、生花、ラジオ、新聞・・・、様々なメディア、身振り、書き物が吟味され、その境界面が明らかにされる。それらの限界芸術としてのふるまいが、ある時は分析的に、ある時は総合的に、そしてある時は歴史として語られる。
鶴見俊輔が日本の先駆者として評価したのが柳田国男だった。柳田が限界芸術の発生を、民謡、鼻歌、流行歌などに留まらず、ゴシップ、なぞなぞ、モノの名前などに見出していたことはすごいと思う。そして近年における祭りの衰えを、演じるものと見る者への分離に帰していたことを知ったが、これはニーチェのギリシャ演劇におけるコーラスの役割の分析に通底する洞察である。改めて柳田国男という民俗学者の奥深さに驚いた。
現代ではアート評論に限界芸術的な論旨を見ることが少なくないが、その前に鶴見俊輔という哲学者、そしてその前に柳田国男という巨人がいたということなのだろう。



コメント